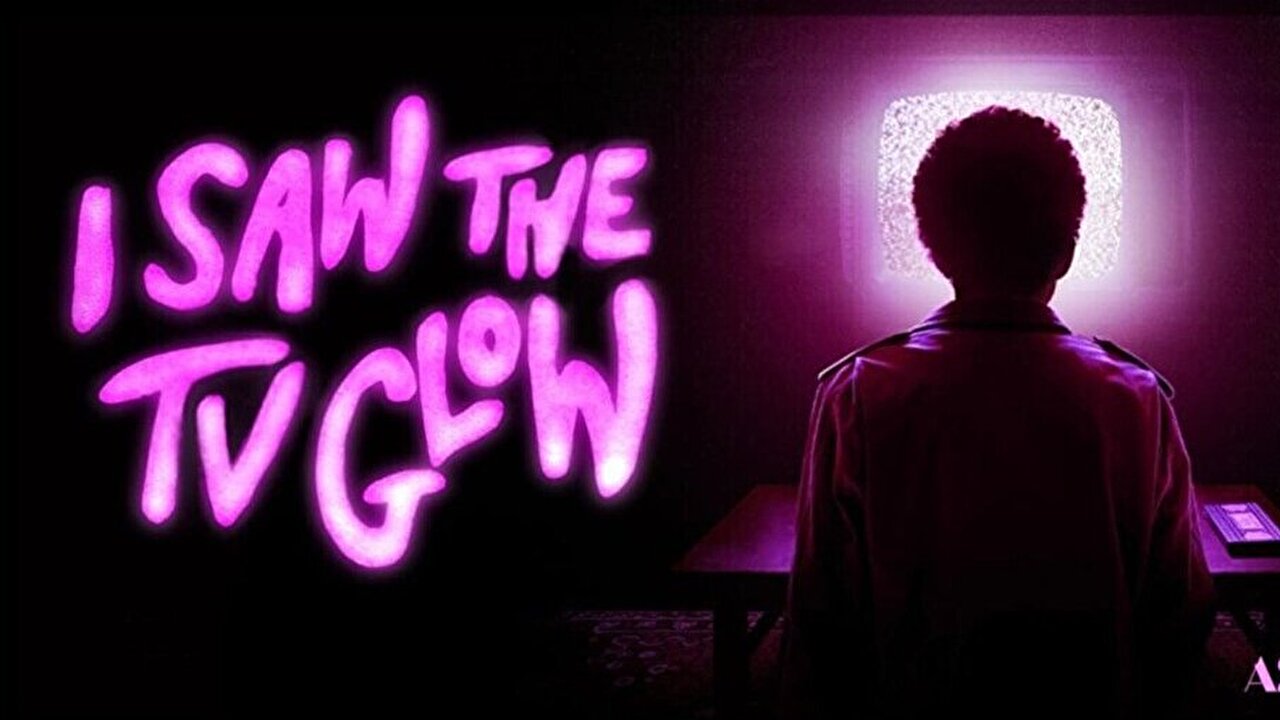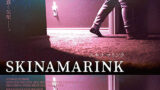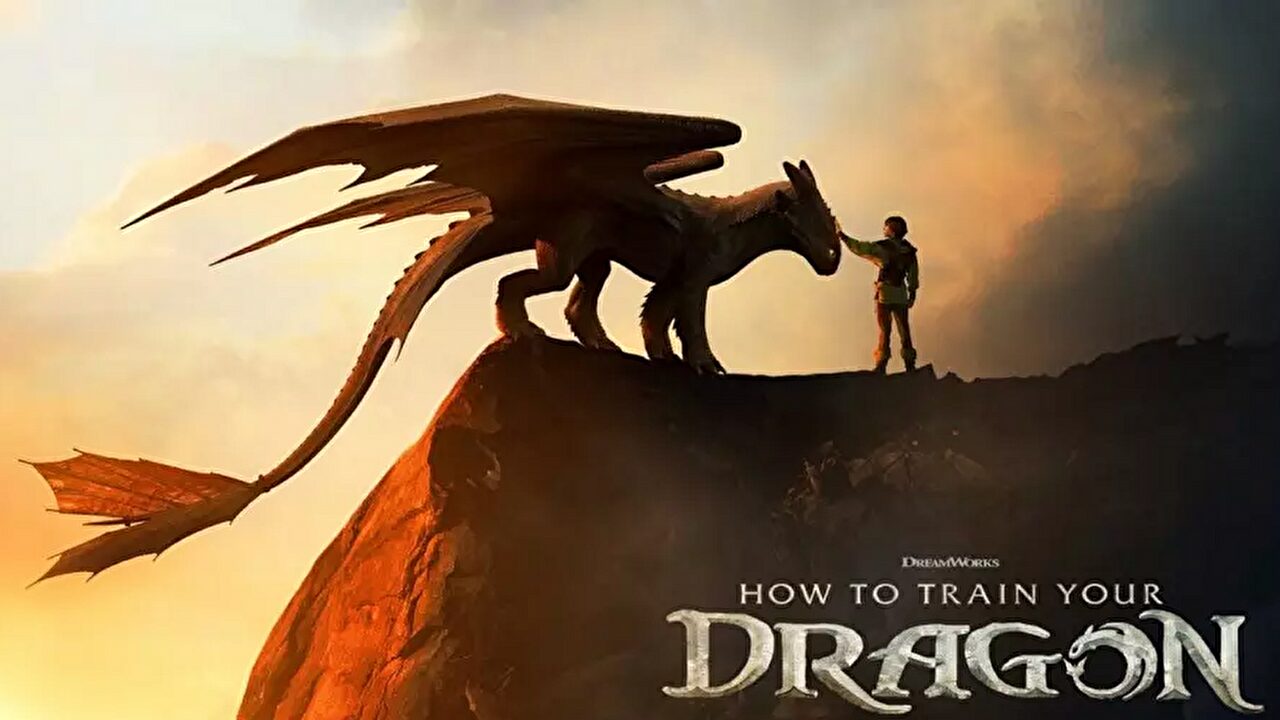タイトルだけなら今年イチにキャッチーな『テレビの中に入りたい』。でも中身は、いわゆるホラーでもスリラーでもなく、ただただ孤独と自分探しを描く“ポエティックアート映画”でした(・ω・)しかも実は“クィア映画”だったらしいのですが…正直私はまったく気づかず(笑)。そんなところも含めて正直にレビュー。ちなみに私が鑑賞した回で「テレビの中に入りたかった」のは、私とおじいちゃんと若い男性の3名でした…。
作品データ
【製作年度】2024年
【製作国】アメリカ
【上映時間】100分
【監督】ジェーン・シェーンブルン
【キャスト】ジャスティス・スミス
ジャック・ヘヴン ほか
あらすじ
生きづらさを抱えたティーンエイジャーのオーウェンはある日、謎めいたクラスメイトの少女マディの家で不思議な深夜のテレビ番組「ピンク・オペーク」を初めて観て魅了される。すっかり「ピンク・オペーク」の虜になったオーウェンだったが、2年後、マディは行方不明となり、番組も終了してしまう。深い喪失感に見舞われ、ただ時間だけが過ぎていく日々を送るオーウェン。8年後、そんな彼の前に行方不明だったマディが現れ、これまでずっと「ピンク・オペーク」の中で過ごしていたと告白するのだったが…。(allcinemaより)
年齢制限は?
PG12指定なので、12歳以下の方は保護者の判断が必要・または同伴が望ましいとされます。
どこで見れる?
レビュー ( 2025・10・03 )
1、タイトルだけなら今年イチ
『テレビの中に入りたい』のキャッチーさ
『テレビの中に入りたい』──正直、作品タイトルだけなら今年イチです(・ω・)子どもの頃に誰しも1度は夢見たようなフレーズで、ノスタルジー全開。
それに加え、まるで『ポルターガイスト』を思わせる、怪しげでアートなポスターに、秒で劇場案件となりました。
ただ、公式では「メランコリック・スリラー、自分探し、幻想的・ホラー的要素あり」などとされており、抽象的な印象(そしてこのテの作品は、私的にキケンw)。
それでも、ど〜うしても気になっていたので、劇場へ足を運んだのですが…。
原題と邦題のニュアンスの違い
やはり…公式ジャンルのテーマに近い“内省的でポエティックな作品”でした(・ω・)
青春こじらせドラマの中に、たまたまホラー的ニュアンスが入っているアート作品、というような。
よく考えたら、原題は「 I Saw the TV Glow」。直訳すると「テレビの光を見た」で、なんとも静かで詩的な響きです。
邦題のように「テレビの中に入る!」と夢や憧れを直接的に示すものではなく、「ただ光を見つめていた」という距離感のあるタイトル。つまり、邦題が観客(私)をワクワクさせすぎてしまったとも言えます。
それでも邦題のインパクトのおかげで、配信された後も「なんだろう、ちょっと気になるな」と、とりあえず再生ボタンを押してしまう人も多そう。
そういう意味では、日本の配給がつけた邦題のセンスは素晴らしかったと感じます。
脚本段階でエマ・ストーンがこの作品に惚れ込み、自身のプロダクション会社「フルーツツリー」との共同製作となったようです。自身もランティモス組で、アート作品にどっぷり浸かっていますからね(・ω・)
2、ホラーでもスリラーでもない?
ざっくりあらすじ
舞台は1990年代のアメリカ郊外。主人公オーウェンは孤独な少年で、現実には居場所がない。
そんな彼が見つけた「救い」が、毎週22:30から放送されているテレビ番組『The Pink Opaque(ピンク・オペーク)』。
イザベルとタラの2人の少女が「Mr.メランコリー」なる敵と戦う…という内容で、一見すると子ども向けのヒーロー番組ですが、雰囲気はなかなかカルト。
上級生のマディもこの番組の大ファンで、2人は一緒に番組を語り合うようになります。しかし次第に、オーウェンとマディはそのキャラクターたちに自分を重ね、現実との境界が揺らぎ始める…。
やがてマディは姿を消し、取り残されたオーウェンは、番組の打ち切りや家族の死を経て、ますます“現実を生きていない”感覚に陥っていくー。
「不穏さ」だけで進む、事件の起こらなさ
本作、血が飛び散るわけでもなければ、連続殺人や分かりやすい怪異が起きるわけでもありません。
映像の雰囲気は常に不穏で、暗い照明やじっとりした空気感で観客を煽るのですが、描かれるのはそこまで…。
起きている物事をそのまま受け取ろうとすると、意味不明ですw
いわゆる雰囲気映画でもあり、物語としての「事件」がほとんど起こらないのです。
普通なら、母の死やマディの失踪など、大きな出来事をドラマとして盛り上げられそうな場面もあります。しかしこの映画は、そうした山場をあっさりスルーし、ただ淡々と「現実に馴染めないオーウェンの日々」を並べていきます。
確かに「不穏さ」や「現実と幻想の境界が崩れていく感覚」は描かれていますが、それをサスペンス的な盛り上げに使うのではなく…
100分間、主人公が内面で迷走し続けるだけ…。
実はクィア映画だった…!?
そしてもうひとつ、あとから知って1番驚いたのが… 実はこの映画、“クィア映画”として語られてるってことなんです。
正直「え、クィア?…どこが……」ってなりました(・ω・)
鑑賞中は一切そんなこと思わなかったし、ただの“孤独で迷走してる主人公の話”にしか見えなかったんですよね。
監督自身がトランスで、「これはクィア的な生きづらさを描いた」とインタビューでは言っているらしいのですが…いやいや、これは言われなきゃ分からないなというレベル(※個人差があります)。
なので、特別“クィア映画”ということを意識しなくても全然大丈夫です。 普通に「不思議な青春ドラマ」として観ても問題ありません。
主人公に共鳴できれば、刺さる
正体はホラーでもスリラーでもなく、アート寄りの青春(クィア)ドラマ。現実に居場所がない人間が、テレビの光や幻想の中に救いを求める物語。
A24っぽいなと言えばそれまでですが、ここ最近のA24作品の中でもかなり難解な方ではないでしょうか…。
ただ一方で、映画評論家や批評好きな人の中にはハマる方も一定数いるようで。Filmarksでも3.7と、これが結構な高評価なんですよね。(ただ、映画.comでは2.9とかなり開きがあります…)
主人公の孤独や“居場所のなさ”に共鳴できる人には、深く刺さる映画なのだろうとも感じました。
現に北米公開時には「若者を中心に大熱狂を獲得した」とのことなので、テーマ的にやはり若者にウケるのでしょうね。
※ここから先はネタバレありで語ります。
気になる方はこちらから鑑賞できます◎
3、徹底排除された“現実ドラマ”
母の死や父との関係を描かないワケ
本作で気になったのは、先ほども言ったように、普通なら“ドラマが生まれるはずの場面”がことごとくカットされていること。
例えば母親。オーウェンの母は病気により亡くなるのですが、死にゆく姿や彼の心情はほぼ描かれません。悲しみに暮れるシーンも、ドラマとしての山場も存在せず。
また父親に至っては、ほとんど他人のように描かれます。
オーウェンがテレビに頭を打ちつけている場面では助けに駆けつけるものの、その後の親子の会話や感情のやり取りは一切描写されません。
あえて「親子の絆」や「家族の愛」といった、観客が共感しやすい要素を徹底的に排除しています。
現実=空白、幻想=唯一の実感
なぜこうした“人間ドラマ”を避けるのか。
それは、オーウェンにとって現実は空白であり、何も意味を持たないからだと感じました。
母の死も、父との距離も、彼にとっては“存在していない”のと同じ。その代わりに唯一色彩を帯び、実感を伴うのが『ピンク・オペーク』というテレビ番組であり、マディとの語らい。
映画全体が「現実の出来事=空虚」「幻想の世界=生の実感」という対比で構築されているため、観客としては私のように「薄い」「物足りない」と感じてしまう人もいるかもしれません。
ですが、それこそが監督の狙い。オーウェンの孤立や生きづらさを体験させるために、あえて現実的なドラマを削ぎ落とす作りになっているのです。
そもそも『ピンク・オペーク』という番組すら、本当に存在していたのか疑わしく思ったりも…。
実は2人だけの頭の中で生み出した“居場所”に過ぎなかったのでは?そう考えると、この映画の幻想性や空虚感がより際立つ気もします。
オーウェンとマディがスーパーで再会するシーン。しかし店内は薄暗く、他の客さえ見当たらない…まるで別世界のような異空間。これも、現実なのか…果たして。
4、主人公2人のクィア的存在
オーウェンの性自認の曖昧さ
さて、本作がクィアを描いたと知った上で考えると、少し違った見方も出来ます。
オーウェンは、子ども時代からずっと「現実に馴染めない」「自分が何者なのか分からない」という違和感を抱えています。
母の死も父との関係も空白のまま。大人になっても、職場でも家庭でも「居場所がない」。恋愛も描かれないし、異性愛的な成長もまったく示されません。
終盤で胸を切り開いて「中にテレビ(別の自分)がいる」と確認するのは、“外側の自分”ではなく“内に秘めた本当の自分”を見たいというクィア的モチーフの極致だったのでしょうね。
外側では誰にも理解されない彼の内面には、“別の自分”が確かに存在している。けれど、それを見せても社会は無反応。彼の停滞は、最後まで解消されないまま残されてしまうのです。
逃げ出すマディの選択肢
一方のマディは、同じように現実に居場所を見いだせない人物ですが、彼女の選択はオーウェンと正反対。
現実を壊してでも「番組の中にいる自分」として生きたいと望み、最終的には現実世界から姿を消してしまいます。
オーウェンが足を止め続けたのに対し、マディは踏み出してしまった。
この対比は、クィア的な存在が抱える2つの道を象徴しているように思えます。
だからこそ、オーウェンとマディの2人は単なるキャラクターではなく、監督自身の体験や視点を反映した“2つの選択肢”として描かれているのかなと思いました。
「現実に留まって苦しみながらも社会に適応しようとする生き方と、現実を拒絶して自分が本当に生きられる世界へ飛び込む生き方」
その両極が同時に提示されるからこそ、観客は2人の姿に強烈な投影を感じてしまうのかもしれません。
5、不可解なラストの意味を考察
イベントスタッフという人生の下降スパイラル
実はこの物語、30年ほどのスパンを描いており、物語の終盤になると20年後へと飛びます。
かつて映画館で働いていたオーウェンは、今やイベントスタッフに。華やかなはずの現場にいても、彼は現実から切り離され、ただ機械的に働くだけの存在。
また、40代とは思えないほど老け込んでおり、疲れている様子。
この「映画館スタッフからイベントスタッフへ」という流れは、彼の人生が下り坂を転がっていく様をそのまま示しているようで、なんだか胸が痛くなりました…。
居場所を見つけられなかった彼が、社会の中でどんどん“意味のない仕事”に追いやられていくー。
「ごめん」に誰も反応しない結末
そしてラストシーン。
オーウェンは突如「死にそうだ」と叫び、トイレに駆け込むと自分の胸をカッターナイフで切り開くのです。
そこに現れるのは、かつて自分を救ってくれたテレビ番組『ピンク・オペーク』の光。内側に秘めていた“もうひとつの自分”を見出した瞬間。
しかし、そのあと服を着直し現場に戻った彼が「ごめん」と小さく謝っても、周囲の人は誰ひとり反応せず、まるでマネキン人形のよう。
社会は彼の存在を気に留めず、彼の叫びも謝罪も届かない。まさに「現実に戻っても孤立は変わらない」という結末。
不可解で観客を突き放すラストですが、同時に監督が描きたかった“クィアとしての孤立”や“本当の自分を見せても社会には届かない痛み”が凝縮されているようにも。
救いのない終わり方に戸惑いつつも、カルト的な熱を帯びた本作らしいラストだったと感じます。
…これぞ、刺さる人には刺さる代表のような本作。私のようにタイトルに惹かれた方は、ぜひご自身の目で確かめてみてください(・ω・)
「夢の中の男」が世の人々を狂わせる!?不思議な寓話
妄想と現実が溶け合う不条理地獄!3時間の不安系珍道中
“何も起きない恐怖”で、観客を置き去りにするカルト映画